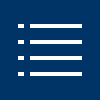2025年6月27日(金)に開催しました2025年度第1回ルーテル・リカレント講座(講師:増本利信教授)にご参加いただき誠にありがとうございました。
寄せられた質問について、講師からの回答は以下のとおりですのでご参照ください。
Q1.
今回の講義の文の見え方のような内容を例えば中学年の児童に話すことで理解を求めることは可能なのか気になりました。
A1.
ご質問ありがとうございます。
見え方の違いを含めて客観的な視点を持つことは相互理解のためにとても重要ですね。
伝え方に工夫は必要でしょうが、子どもたちも理解することは可能だと思います。
Q2.
我が娘は、現在、小5で入学後に学習への遅れが顕著で、受診し自閉スペクトラム症の診断で、小2より算国を特別支援学級で学んでおります。
どの教科も苦戦しておりますが、特に算数が理解に苦しんでます。今は割り算なので、ちんぷんかんぷんと言ってます。
算数苦手の仕組みを理解したいのと支援の方法等について学びたいと思ってます。
A2.
お尋ねをありがとうございます。
算数の困難さについては非常に幅が広いですね。数を扱う能力を高めておくことはとても大切ですので、トランプで7並べを行うなど、楽しんで数の大小等を扱う活動を仕組まれるのも良いかなと思います。
何より、生活の中で算数の考えた方を活かせるような言葉掛けや、学んだことが生活で役に立つ実感を持たせることも重要なことかなと思います。親子で楽しんで取り組まれてください。
Q3.
子どもが困り感を抱える前に、教員側からアプローチするというのは“理想“だなと思いました(できたらいいなと思いました)
現場では静かな障害児は、害がないから放置されますよね。声をあげないと、支援はしてもらえない。
A3.
ご参加ありがとうございました。
おっしゃる通りで、静かな困りは見過ごされる事が少なくありません。その反省に立ち、早期のスクリーニングで困る前に注意を向けるべき児童生徒を見つける動きや手法も開発されてきました。今後も広まるといいなと思っています。
Q4.
今回、特に周囲の指導への支援について学ぶことができ参考になりました。特に、規範意識を持っているこどもたちや教師から関わりの少ないこどもたちに対して、これまでにうまくいった具体的なかかわり方はありますか?
A4.
ご参加ありがとうございます。
規範意識があるが故に教師からの関わりが少ない子どもたちに対しては、私自身も反省する事が少なくありません。つい気になる児童に教師の注意が向き過ぎてしまいがちになってしまいます。その中で効果的だったのは、5年生担任時に、先生が教室を離れる際に取り組む自習を常に準備してもらう関わりがありました。この時は「読書」と「漢字練習」を自習でのおすすめ課題として、常に机の中に準備しておくように指示し、適宜取り組むよう指示をしました。先生がいる時間も授業終盤に5分程度残ったら「自習」をするなど活用していました。自然と子どもたちは、授業中に手持ち無沙汰になったら、サッと本を出したり、漢字ノートを出したりするようになり、私も褒める事が多くなったのでいい循環となった事があります。
「すべきことを明確にする」「きちんと褒める」事が大切だったなと思いました。